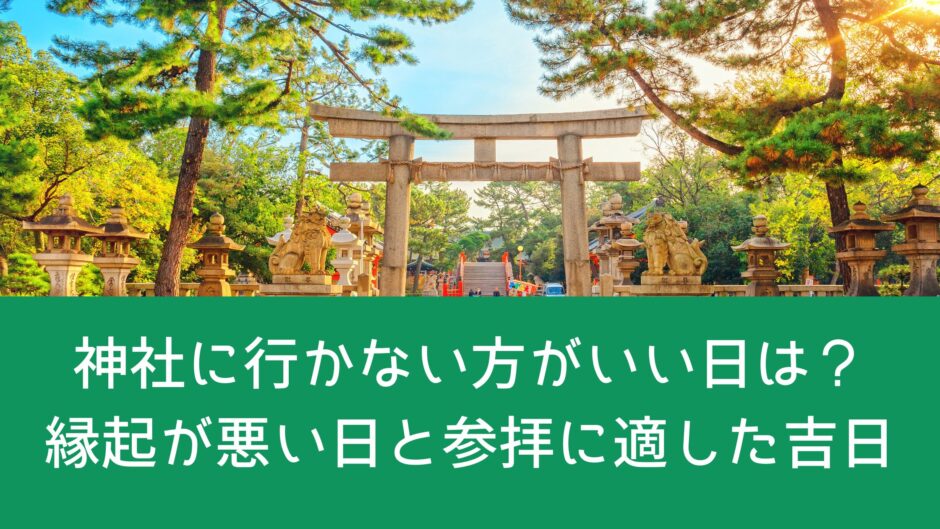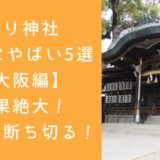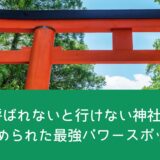神社に行かない方がいい日はあるのでしょうか?この記事では、六曜や物忌みなど、神社参拝に縁起が悪いとされる日と、大安、一粒万倍日といった吉日について解説します。また、仏滅に参拝してはいけないのか、吉日を選ばないとご利益がないのかなど、よくある疑問にもお答えします。さらに、正しい参拝マナーも紹介することで、安心して神社にお参りできるよう、神社参拝に関する不安を解消します。
目次 閉じる
神社に行かない方がいい日とは

古来より、日本では神社への参拝は神聖な行為とされ、日取りを気にする風習があります。特に結婚式や地鎮祭などの重要な儀式の際は吉日を選ぶことが一般的ですが、普段の参拝でも縁起を担いで日取りを選ぶ人も少なくありません。では、具体的にどのような日が「神社に行かない方がいい日」とされているのでしょうか。それは大きく分けて、六曜によるものと、その他の伝統的な暦注によるものがあります。
六曜による縁起の悪い日
六曜とは、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6種の曜日のことで、暦注の一つです。日本では古くから日々の吉凶を占う際に用いられてきました。六曜の中で、一般的に神社への参拝を避けた方が良いとされる日は以下の通りです。
仏滅
仏滅は六曜の中で最も縁起が悪い日とされています。「仏も滅するような大凶日」という意味があり、結婚式や祝い事、新規事業の開始などは避けるべきとされています。神社への参拝も同様に、避けた方が良いと考える人が多いようです。特に、お祝い事やお願い事などの祈願を目的とした参拝は、仏滅を避けるのが無難でしょう。しかし、日常的な感謝の祈りを捧げる場合は、必ずしも仏滅を避ける必要はないという考え方もあります。
友引
友引は、朝夕は吉、昼は凶とされる日です。特に「友を引く」という字面から、葬儀を執り行うことは避けるべきとされています。神社参拝に関しては、午前中または夕方であれば問題ないとする説や、「友を引く」ことから、良い運気を他の人と分かち合うという意味で吉日とする説もあります。ただし、地域によっては友引に葬式を執り行うこともあり、その場合は神社参拝も避けるのが望ましいでしょう。
その他の縁起の悪い日
六曜以外にも、神社への参拝を避けるべきとされる日がいくつかあります。これらは、古くからの言い伝えや風習に基づいています。
物忌み
物忌みとは、神道の祭祀において、一定期間、特定の行為を慎むことを指します。神社によっては、特定の日に物忌みが設けられており、その期間中は参拝を控えるべきとされています。神社によって物忌みの日は異なるため、事前に確認しておくことが大切です。物忌みの期間や内容は、神社の公式ウェブサイトや掲示などで確認できます。
参拝に適した吉日

神社への参拝は、日取りを選ぶことでより良い効果を期待できるとされています。吉日を選んで参拝することで、神様への敬意を表し、自身の願いがより届きやすくなると考えられています。ここでは、代表的な吉日について解説します。
六曜による吉日
六曜は、暦注の一つで、先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の6種類があります。その中でも、特に吉日とされるのが、大安、先勝、友引です。
大安
大安は、六曜の中で最も吉日とされています。何事においても成功しやすい日とされ、結婚式や開店など、お祝い事にも最適です。一日を通して吉なので、神社参拝にも良い日と言えます。
先勝
先勝は、「先んずれば即ち勝つ」という意味で、午前中は吉、午後は凶とされています。神社参拝は午前中に行うのが良いでしょう。急用や、勝負事、仕事始めなどに適しています。
友引
友引は、「凶事に友を引く」という意味から、葬儀には避けられる日ですが、祝い事には吉とされています。朝晩は吉で、昼間は凶と言われています。神社参拝も、朝か夕方に行うのが良いでしょう。ただし、友引に葬式を執り行う地域もあるので注意が必要です。お祝い事全般、契約事、開店、移転、旅行などに適しています。
その他の吉日
六曜以外にも、様々な吉日があります。中でも代表的なのが、一粒万倍日、天赦日、寅の日です。これらの吉日は、それぞれ異なる意味を持ち、重ねて訪れることもあります。
一粒万倍日
一粒万倍日は、「一粒の籾(もみ)が万倍にも実る」という意味で、何かを始めるのに非常に良い日とされています。事業開始、開店、結婚、投資など、新しいことを始めるのに最適です。神社参拝で新たな目標を祈願するのも良いでしょう。特に、金運アップを願う参拝に適しています。
天赦日
天赦日は、百神が天に昇り、天が万物の罪を赦(ゆる)す日とされ、日本の暦の上で最上の吉日とされています。年に5~6回しか訪れない貴重な日で、結婚、開業、引っ越しなど、重要なことを始めるのに最適です。神社参拝で、日頃の罪を悔い改め、新たなスタートを切ることを祈願しましょう。特に、厄除けや祈願成就の参拝に適しています。
寅の日
寅の日は、虎は千里を行って千里を帰ることから、出て行ったものがすぐに戻ってくるという意味で、金運に関する吉日とされています。財布の新調や宝くじの購入、旅行などに良い日とされています。神社参拝で金運上昇を祈願するのも良いでしょう。特に、毘沙門天や弁財天など、財運の神様を祀る神社への参拝がおすすめです。
これらの吉日は、単独で訪れることもあれば、複数重なることもあります。例えば、大安と一粒万倍日が重なれば、さらに大きな吉日となります。複数の吉日が重なる日は、積極的に神社に参拝し、自身の願いを祈願しましょう。ただし、吉日はあくまで目安であり、絶対的なものではありません。大切なのは、神様への敬意を払い、誠心誠意参拝することです。
神社の参拝マナー
神社に参拝する際には、神様への敬意を表すため、いくつかのマナーを守るようにしましょう。服装、鳥居のくぐり方、参拝方法など、基本的なマナーを理解することで、より丁寧で気持ちのこもった参拝ができます。
鳥居のくぐり方
鳥居は神域と人間の世界を分ける結界です。鳥居をくぐる際は、一礼してから進みましょう。中央は神様の通り道とされているため、中央を避けて、左右どちらかを通るのがマナーです。また、鳥居の前で立ち止まっておしゃべりしたり、写真を撮ったりするのも避けましょう。
鳥居の種類と意味
神社には様々な種類の鳥居があります。代表的なものとしては、明神鳥居、神明鳥居、両部鳥居などがあります。これらの鳥居はそれぞれ形状や由来が異なり、神社の歴史やご祭神を反映しています。鳥居の種類を知ることで、より深く神社を理解することができます。
参拝方法
神社の参拝方法は一般的に「二拝二拍手一拝」です。まず、賽銭箱の前に立ち、軽く一礼します。次に、賽銭を静かに入れ、二回深くお辞儀をします。その後、両手を胸の高さで合わせ、右手を少し下にずらして二回拍手を打ちます。最後に、もう一度深くお辞儀をして参拝を終えます。ただし、神社によっては「二拝四拍手一拝」や「一拝一拍手一拝」など、異なる作法のところもあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
手水舎での作法
参拝の前に、手水舎で手と口を清めるのがマナーです。柄杓を右手に持ち、水を汲んで左手を清めます。次に柄杓を左手に持ち替えて、右手を清めます。再び柄杓を右手に持ち、左手に水をためて口をすすぎます。最後に柄杓を立てて残った水で柄杓の柄を洗い流し、元の位置に戻します。一つの柄杓で水を二度汲まないように注意しましょう。
お賽銭の意味
お賽銭は、神様への感謝の気持ちを表すものです。金額に決まりはありませんが、自分の気持ちを表す金額を納めましょう。投げ入れるのは失礼にあたるので、静かに賽銭箱に入れましょう。
まとめ
この記事では、「神社に行かない方がいい日」について解説しました。六曜における仏滅や友引、その他物忌み、八専といった日は、古くから避けるべき日とされています。特に仏滅は万事に凶とされるため、冠婚葬祭など重要な行事は避ける人が多いです。友引は「友を引く」という意味から、葬式を避けるべき日とされています。しかし、これらの日はあくまで迷信に基づくものであり、必ずしも悪いことが起こるわけではありません。
一方で、大安や先勝、友引、一粒万倍日、天赦日、寅の日は吉日とされ、神社への参拝に適しています。特に大安は六曜の中で最も吉とされる日であり、多くの人が結婚式や引っ越しなどを選ぶ日です。これらの吉日は何かを始めるのに良い日とされていますが、吉日だからといって必ず成功するとは限りません。
神社への参拝は、日取りよりも自身の気持ちが一番大切です。吉日を選んで参拝するに越したことはありませんが、どうしても都合がつかない場合は、無理に吉日にこだわる必要はありません。敬虔な気持ちで参拝すれば、きっと神様は気持ちを受け取ってくれるでしょう。服装や鳥居のくぐり方、参拝方法といった基本的なマナーを守り、感謝の気持ちを持って参拝しましょう。